
右脳と左脳をコンピュータで再現。これが次世代AIだ!
AIに右脳と左脳はあるんでしょうか? 次のAIといわれる汎用人工知能は、人間と同等の知能を持つそうです。 さらに、人間を超えた超知能の出現ま...
次世代AIの提言 AIの意識×言語の意味理解 Next ChatGPT いかにして意識を発生させるか。分かりやすく動画で解説。
Eden -AIの暮らす街- 意識が宿ったAIをアニメで紹介
僕たちが必要としているのは、「あれをやって」と頼めば何でもやってくれる人工知能です。
かといって、世界チャンピオンに勝つような難しい仕事を頼みたいわけではないのです。
頼みたいのは、人間なら誰でもできる簡単な仕事です。
ちょっとした調べ事を頼んだり、ちょっと、話し相手になってもらったり。
人間のように、何でもできる人工知能、これを汎用人工知能(AGI: artificial general intelligence)といいます。
汎用人工知能こそ、今、もっと求められている技術です。
汎用人工知能ができれば、シンギュラリティが起こると言われています。
でも、汎用人工知能を作るには、とても大きな壁があります。
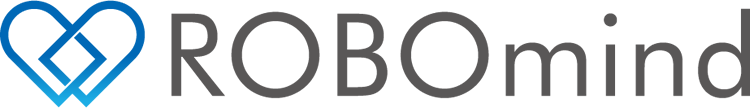
「あれをやっておいて」と、人間のように頼めば何でもやってくれる人工知能。
それだけのことが、なぜ、できないのでしょう?
人は、人に頼むとき、言葉(自然言語)で説明します。
頼まれた人は、言葉の意味を理解して、その通りの仕事をします。
実は、AIには、これができないのです。
そもそも、「言葉の意味を理解する」とは、どういうことなのかさえ、未だにわかっていません。
ロボマインド・プロジェクトでは、言葉の意味を理解するために、人間と同じ心のモデルを開発しました。
コンピュータに意識を発生させる仕組みを開発しました。
㈱ロボマインドは、「言葉の意味理解」を実現できる世界で唯一の会社です。

AIに右脳と左脳はあるんでしょうか? 次のAIといわれる汎用人工知能は、人間と同等の知能を持つそうです。 さらに、人間を超えた超知能の出現ま...
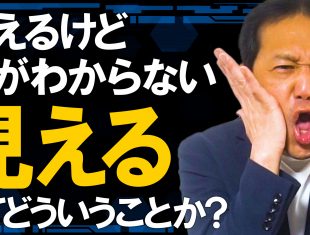
「見る」って、考えれば考えるほど不思議です。 「見る」って、ただ、世界にあるものを見てるだけって思っていました。 ところが、そうじゃない...
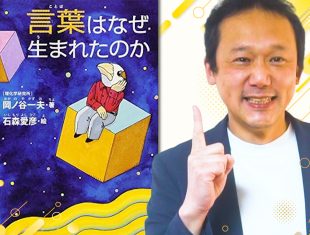
いまや、動物が言葉を話すのは当たり前になってるようです。 言葉をしゃべるのは人間だけだって思ってましたけど、そんなわけはないです。 以前...

AIの進化が止まりません。 動画を生成したり、ロボットに搭載されたり。 かつて、AIは記号接地問題を解決できないと言われていました。 シンボ...

ロシアのプーチン、北朝鮮の金正恩が怖いのは、何をしでかすか分からないからです。 核をもってるからなおさらです。 とはいえ、目的は明確です...

今年は、ロボマインドはアカデミアにも進出しようとしています。 そこで、分野的に一番近い「汎用人工知能研究会」で論文発表してきました。 汎...

脳はなぜ、右脳と左脳に分かれているのでしょう? これがよく分かりません。 もちろん、右半身は左脳、左半身は右脳が制御するって役割分担する...

またまた驚愕の言語学仮説です。 もちろん、提唱してるのは僕ですけど。 でも、今回の仮説、かなり信憑性が高いんです。 言葉に、元々意味なん...
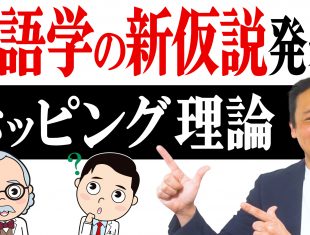
言語学は文系じゃないですよ。 言語って、あれだけ複雑な処理をするんだから、コンピュータでないと対応できません。 だから、言語学はコンピュ...

失語症ほど、言葉について理解できるものはありません。 言葉というものは、脳の中で処理されています。 だから、脳を損傷して言葉がでない失語...
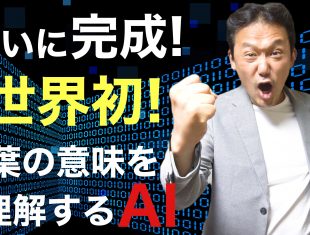
ついに公開します。 開発中の自然言語の意味理解システム マインド・エンジン 絶対不可能と言われてきた、自然言語の意味理解。 なぜ...
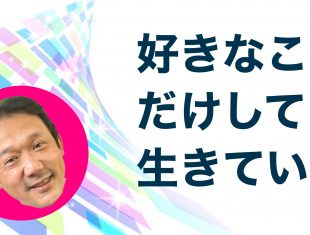
今回は、インタビュー動画です。 早いもので、僕が、この研究を始めて、20年にもなります。 まさか、こんなに続けてるとは、思ってもみません...

フレーム問題って何? AIの歴史について調べていると、必ず出てくるのが人工知能最大の難問と言われる「フレーム問題」です。 フレー...

現在は第3次AIブームと呼ばれ、その主役は、ディープラーニング(深層学習)です。 ディープラーニングは、学習によって自動で特徴量を抽出でき...